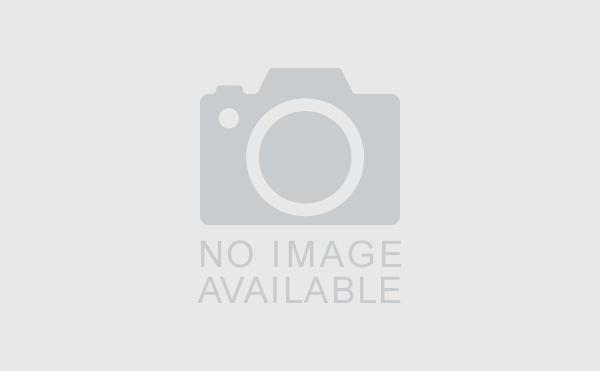初の国産旅客機 YS-11設計者 木村秀政①
見渡す限りの航空機の群れ。着陸体勢に入った五機が進入ルートに沿って一直線に見える。二分に一回、一日約八百便が発着する羽田空港。平成十三年六月三十日、ボーイング、エアバスなどの欧米機に交じって大島路線を飛んでいた唯一の国産旅客機「YS-11」が退役、羽田空港から日本の翼が消えた。この日から順次、YSー11は退役する。戦中に世界に誇る傑作機を設計した「零戦」の堀越二郎、「飛燕」の土井武夫、「隼」の太田稔、「紫電改」の菊原静男、そして、「航研機」の木村秀政がYSの設計に携わった。世間は映画『七人の侍』にかけて、「五人のサムライ」と呼んだ。
* * *
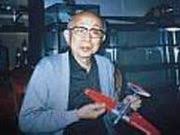
零戦の堀越、飛燕の土井、隼の太田、紫電改の菊原、航研機の木村
大正二年三月二十八日。搭乗者二人が死亡する日本で最初の航空機事故が起きた。八歳だった木村秀政は、この日を克明に記憶していた。

東京・青山に住んでいた木村は青山練兵場で三機の飛行機を見た。間近に見るのは初めてだった。特に単葉機の「ブレリオ」を「キリッと無駄のない設計。美しかった」と記憶。飛び立ったブレリオを見えなくなるまで見送った。
自宅に帰った木村は早速、翼の骨組みまで精密に描いて、近所の子供に自慢していた。そのとき、号外の鈴音が鳴った。墜落事故の知らせだった。『あの精巧な機体がバラバラになって、二人が死んだ。悲壮感を持って幼い私の胸を強く打った』と書き残している。美しい機影の残照と凄惨(せいさん)な事故。航空機には表裏一体の姿があった。このとき木村の進む道が決まった。
府立第四中学(現・都立戸山高校)、第一高等学校と進んでも、飛行機のことが頭から離れず、付いたあだ名はそのまま「ヒコーキ」。大正十三年、東京帝国大学構内に張り出された航空学科の合格者八人のなかに木村の名があった。「零戦」の堀越二郎、「飛燕」の土井武夫もいた。航空日本の幕が開きつつあった。
「速く」「高く」「遠く」。航空機技術の三大目標のうち、どんなに木村の業績を調べても、最も華やかな「速く」に興味を示した記述はない。
「基本的な考え方は操縦者、整備者、乗客、使用会社など使う人の立場に立った航空機。どんなことをするにも安全が最優先された。だから自然とスピードは後回しになったのではないか」と日大教授の柚原直弘さんは説明する。
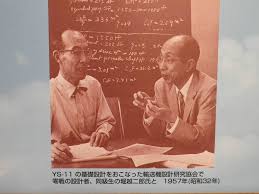
速さよりも、安全な航空機を
その木村の卒論のテーマは「安定性・操縦性」。幼いころの事故の記憶が「安全な航空機開発」に向かわせたのか。
「遠く」への挑戦は卒業後、東大航空研究所に入って、すぐに始まった。昭和八年、世界記録を目指す長距離機「航研機」開発がスタートした。
木村は胴体、着陸装置などの設計を担当、特に日本初の引き込み脚に苦心した。当初は油圧式だったが、テスト飛行の際には脚が出ないまま着陸したこともあり、手動式に変更。飛び立った鳥が優雅に脚を体に収めるようにはいかなかった。
中国・満州に不時着しても探し出せるように、両翼を深紅に塗られた機体が完成したのは四年後の十二年。空気抵抗をなくすため、操縦者は胴体内にスッポリと収まり、前方がまったく見えない。フランスの一万六百一キロを破る世界記録だけが目的の飛行機だった。それぞれの職人意識が濃厚だった時代。操縦者に拒否されるかと不安だったが、「よろしい、これで飛ぼう」と快諾された。

世界記録二つ 長距離の無敵王 航研機
昭和十三年五月十三日、気象台の予報は無風快晴。午前五時、七千五百リットルのガソリンを詰め込んだ航研機は、千葉・木更津航空隊の滑走路を千三百メートルも滑走してヨレヨレと飛び立った。
コースは木更津-千葉・銚子-群馬・太田-神奈川・平塚の一周約四百キロ。深紅の翼が関東上空を昼も夜も飛び続けた。ラジオや新聞は『もう何周、あと何キロ』『航空日本きょうぞ制覇の日』と報道、オリンピックのように日本中の人々の血をわかせた。

しかし、三日間も機内にいた機関士の関根近吉は「心身の疲労からまどろんで、ふと目覚めると停止したような錯覚を起こした」と語っている。無線機が積まれていないため、地上ではエンジン音で調子を判断するしかなかった。
太田で計測していた細井正吾さんも二時間おきに飛来する爆音に耳を澄ましていた。来るたびに「まだ大丈夫。いい音だ」と話し、記録達成を待った。三日目の夕方、二十九周目が飛来してきた。「来た。世界記録だ」。細井らが万歳をする上空を航研機はゆっくりと南に進路を変えた。機内では用意していたシャンパンで乾杯をした。
しかし、その直後から雨が降り始めた。まだガソリンは残っていたが、飛行を断念、木更津に降り立った。記録は六十二時間二十三分、一万千六百五十一キロ。現在まで航空機の公認世界記録はこのひとつしかない。新聞は『双翼に燦 世界記録二つ 長距離の無敵王』とかき立てた。国民も欧米の航空先進国に追いついたように熱狂した。
* * *
羽田空港に埋められたままの航研機
羽田空港の旧B滑走路。この地下に航研機が埋められている。敗戦後、羽田に進駐した米軍は格納庫にあった航空機をブルドーザーですべて鴨池に捨てた。このなかに航研機も含まれていたという。鴨池は埋められ、現在の旧B滑走路になった。

「だれも見た人はいないけど、そう聞いています」と細井さんは思い起こすようにいった。欧米の大型機が行き交う下に航研機が埋もれている。やりきれなさが胸の奥底に残った。
日本の航空界にとって敗戦は終わりではなく、「空白の七年」の始まりに過ぎなかった。